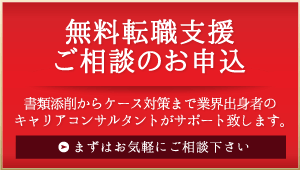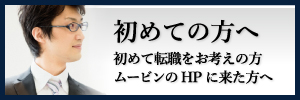- ITコンサルタント転職・コンサルタント転職TOP >
- ITコンサルティング業界情報 >
- IT業界、コンサルティング業界ニュース >
- “竜を飼いならせ”--デジタル化経済に立ち向かうCIOの理想像:ガートナー
“竜を飼いならせ”--デジタル化経済に立ち向かうCIOの理想像:ガートナー
企業ITを支える最高情報責任者(CIO)の役割は大きく変わるのかもしれない。コンシューマライゼーションの動きが象徴的に示しているように、ワールドワイドで“デジタル化(Digitalization)”がすべてを変えつつあるからだ。
ガートナー ジャパンは3月12日、世界のCIOに対する調査をまとめた「CIOアジェンダ調査(2014 CIO Agenda)」の結果を発表した。ガートナーが毎年実施している調査で、今回の対象CIOは77カ国2339人、IT支出の合計は3000億ドル。CIOがデジタル化に対応していくためには「強い『デジタルリーダーシップ』の確立(Create powerful digital leadership)」「ITの『コア』の刷新(Renovate the core)」「2つの流儀の習得(Build bimodal capability)」の3つの施策が必要だと提唱している。
デジタル化という“ドラゴン”
同調査では、デジタル化を“竜(ドラゴン)”になぞらえており、タイトルとして「デジタルという名の竜を飼いならせ(Taming the Digital Dragon)」が付けられている。発表にあたったエグゼクティブ プログラム(EXP) グループバイスプレジデントの長谷島眞時氏(元ソニーCIO)は「ドラゴンは、脅威ととらえ排除する準備を進めるのか、機会ととらえ飼いならす準備を進めるか、の岐路に立っていることを意味している。飼いならすために何をすべきを提言している」と説明した。
ガートナーでは、デジタル化を今後到来する企業ITの「第三の時代」に位置付けている。ここで言う、第一の時代とは「職人的なIT(IT craftsmanship)」で“テクノロジ”にフォーカスし、能力として“プログラミング、システム管理”が求められる時代だったという。どことつながっているか(engagement)については「内部、外部とつながりがなく、孤立した状態」だった。
そこから進んだ第二の時代が「ITの工業化(IT industrialization)」になる。テクノロジから“プロセス”にフォーカスするようになり、求められる能力は“ITマネジメント、サービスマネジメント”になった。つながりは、「顧客としての同僚(サービス利用者が社内の人間)で、最終顧客とはつながっていない状態」となった。
「今われわれは、ITの工業化時代からデジタル化時代への過渡期にいる。デジタル化時代はこれまでのシステムをリプレースするのではなく、そこに追加されるかたちになる」(長谷島氏)
具体的には、デジタル時代にフォーカスするのが“ビジネスモデル”であり、求められる能力は“デジタルリーダーシップ”であり、つながりは「パートナーとしての同僚で、最終顧客とつながる状態」になる。
デジタル化の兆候は、IT予算がどこで何に使われ出しているかからも分かるという。2013年〜2014年のIT部門の増減率は0.2%増だったが、どこで発生しているかに注目すると、IT部門管轄が73%であるのに対し、マーケティング部門管轄が7%、他ビジネス部門管轄が20%となり、IT支出の27%はIT部門予算外で発生していたことがわかった。
「日本から84人の回答があったが、日本の場合はIT部門以外の支出が32%とグローバル平均よりも5%ほど高い。IT予算外の支出があることはガバナンスにかかわるので、過少申告しているケースもあると思われる。実際には、グローバルでももう少し高いのではないか。IT部門を介さずに直接ビジネス部門が導入するITは今後も増える傾向がある」(長谷島氏)
経営者がITに何を期待するかについても「成長とイノベーション」「俊敏性」「完全性」「有効性」「効率性」の経年の変化を取っているが、それをみると、成長とイノベーションの割合が年々増え、効率性が年々下がってくる傾向が確認できるという。一般に“ITに保守的”と言われる日本のデータを見ても「2013年から2014年にかけて、成長とイノベーションが21%から23%に増え、効率性が29%から26%に下がるなど、グローバルと差がない」(長谷島氏)状態になってきているという。
「身のまわりを見渡しても、デジタルテクノロジがエポックメイキングな変化を起こしている。これは、今までのビジネスモデルを根底から変える変化であり、新しい収益源を生む変化でもある。だが、多くの企業はこうしたデジタル化の変化に対応できていない。『IT組織では来たるべき難題に立ち向かうために適切なスキルとケイパビリティが整備されている』との問いに「該当しない」と回答したのはグローバルで42%、国内では57%に上った」(長谷島氏)
デジタル化に対応するための3つの施策
デジタル化に対応するために、ガートナーが提案するのが3つの対策だ。1つめは「強い『デジタルリーダーシップ』の確立」。具体的には、デジタル化を組織として推進する体制を作ったり、“最高デジタル責任者(Chif Digital Officer:CDO)”といったデジタル化担当役員を設置したりといった取り組みだ。
CDOの設置率はグローバルで6.6%、国内で2.2%だが、今後1〜2年で3倍程度に増える見込みだという。経歴としては、マーケティング、IT、ビジネス戦略を経験した担当者がCDOにつく割合が高かった。レポートラインは最高経営責任者(CEO)が42%、最高マーケティング責任者(CMO)が22%、CIOが16%となった。
「まったく新しい職ではなく、デジタル化推進のエバンジェリストのようなイメージだ。デジタル化がすべての領域で進めば、将来的にはなくなるファンクションでもある。本来的にはCEOが担うことが望ましい。デジタルへの精通度が高いCEOとビジネスの成長には相関があることもわかっている」(長谷島氏)
2つめは「ITの『コア』の刷新」。コアというのは、クラウドやウェブのインフラ、情報、人材、ソーシングなどに関するIT戦略を見直すことだ。具体的なIT施策としては、4つの領域があるという。ポストモダンERP/アプリ(Postmodern ERP/apps)、より多様なパートナーシップ(More-diverse partnerships)、次世代の情報分析能力(Next-generation information capabilities)、ハイブリッドクラウド(Hybrid cloud)となる。
ここで注目できるのは、クラウドへの投資理由が「コスト削減」から「俊敏性への獲得」に移り変わってきていること、ソーシングの関係を変える意向が高まってきていることだという。クラウドの導入理由としてコストを上げたのは14%であるのに対し、俊敏性は50%に上った。ソーシングについては80%の回答者が「今後2〜3年のうちにソーシング関係を変える予定だ」とし、46%は「新しいカテゴリのパートナーと協業する必要がある」とした。
3つめの「2つの流儀の習得」は、従来型モードのITとノンリニアモード(非線形)のITというスピードの異なる2つのIT(Two-speed IT)の両方に対応できる組織やチーム、スキルを作ることを指している。ここで言う、従来型のIT(conventional)の特徴は、ウォーターフォール型開発、馴染みのベンダー、厳格なガバナンス、最小化されたリスク、テクノロジチームなどとなる。一方、ノンリニアモードのIT(nonlinear)の特徴は、アジャイル開発、小規模/革新的パートナー、簡易的、丁度良いガバナンス、管理されたリスク、専門家混成チームなどとなる。
「安定や確実性が求められる場合は従来型モード、スピードやイノベーションが必要で不確実が高い場合はノンリニアモードといったように、2つの流儀を使い分ける。それにより、新しいITに対応できず、身動きが取れなくなる事態を防ぐことができる。調査の結果、45%のCIOはアジャイルを特徴とするノンリニアモードのオペレーションを構築していた。だが、大半は2つの流儀をまだ生かしきれていない。全体の準備という点ではまだまだという状況だ」(長谷島氏)
2つの流儀に対応する上では、現在ある組織にCDOを中心としたプロダクトごとの専門家混成チームなどをアドオンするかたちが望ましいとした。
Keep up with ZDNet Japan
ZDNet JapanはFacebook、Twitter、RSS、メールマガジンでも情報を配信しています。
2014年 3月21日
参照ZDNet Japan
ガートナー
顧客には数々の大手企業や政府機関が名を連ねており、IT系企業や投資組合なども多い。リサーチ(Gartner Research)、エグゼクティブプログラム(Gartner Executive Programs)、コンサルティング(Gartner Consulting)、イベント(Gartner Events)から構成されている。1979年に設立され、3700名の従業員のうち 1200名がアナリストやコンサルタントとして世界75カ国で活動している。
ガートナーについて
IT業界、コンサルティング業界の最新ニュースをお伝えします。最先端の業界で何がどう動いているのかをWatchすることで、広くビジネス界全体の今後の動きを展望することができるはずです。
- コンサルティング業界概観
- コンサル採用動向
- セミナー情報
- 企業・ファームインタビュー
- 特集 コラム
- ITコンサルタント向け推薦書籍
- メールマガジン
- ファームランキング
- ファーム出身者
- 用語集
- 業界ニュース
Warning: include(../../naviadd.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 183
Warning: include(): Failed opening '../../naviadd.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/lib/php') in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 183
Warning: include(../../seminar_box.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 186
Warning: include(): Failed opening '../../seminar_box.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/lib/php') in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 186
Warning: include(../../job_box.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 189
Warning: include(): Failed opening '../../job_box.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/lib/php') in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 189
Warning: include(../../footaddobi.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 200
Warning: include(): Failed opening '../../footaddobi.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/lib/php') in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 200
Warning: include(../../foot.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 204
Warning: include(): Failed opening '../../foot.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/lib/php') in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 204
Warning: include(../../head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 212
Warning: include(): Failed opening '../../head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/lib/php') in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 212
Warning: include(../../menu.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 217
Warning: include(): Failed opening '../../menu.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/lib/php') in /home/consul-movin/www/it-movin.co.jp/view/news/headline.php on line 217